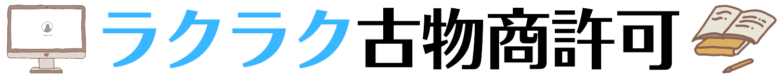古物商許可を取得した事業者は、許可内容に変更が生じた場合、公安委員会への変更届出が義務付けられています。この届出は、古物営業法に基づき、古物市場の健全な運営と犯罪防止を目的としています。
届出を怠ると、罰金や許可取り消しなどのペナルティが科される可能性があり、事業運営に大きな影響をおよぼしかねませんので、十分にご注意ください。
本記事では、古物商許可の変更届出が必要なケース、届出期限、提出先、ペナルティ、よくある質問などを網羅的に解説します。古物商として適正な事業運営を行うために、ぜひ本記事を参考にしてください。
参考:「古物営業の内容に変更がある場合の手続き|変更届出と書換申請が必要な場合について解説」
1.古物商許可の変更届出が必要なケース
古物商許可を取得した後、事業内容や個人情報に変更があった場合は、速やかに変更届出を行う必要があります。変更届出は、変更内容によって事前届出と事後届出の2種類に分けられますので、把握しておきましょう。。
1)変更届出が必要なケースの具体例
①事前届出(営業所に係る変更届出)
・営業所を移設した
・営業所を増やした
・営業所を廃止した
・営業所の名称を変更した
・主たる営業所が変わった
②事後届出
・許可者の自宅住所、姓名が変わった
・営業所管理者が替わった
・営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
・法人の名称、所在地が変わった
・法人の代表者、役員が替わった
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
・行商の「する・しない」の変更
・取り扱う古物の区分変更
・ホームページを開設した古物営業を始めた
・届出のURLを変更した
・届出のホームページを閉鎖した
2)変更届出の重要性
これらの変更届出は、古物商が適法に事業を継続するために不可欠です。変更届出を怠ると、古物営業法違反となり、罰則や許可取り消しの対象となる可能性があります。また、変更内容を適切に管理することは、顧客や取引先からの信頼を得る上でも重要です。

2.変更届出の期限と提出先
変更届出には、届出期限と提出先が定められています。期限内に適切な方法で届出を行うことが重要です。
1)変更届出の期限
①事前届出(変更の3日前まで)
営業所の移転や名称変更など、事前に届出が必要な場合は、変更日の3日前までに届出を行う必要があります。
②事後届出(変更から14日以内)
許可者の住所変更や営業所管理者の変更など、事後に届出が必要な場合は、変更日から14日以内に届出を行う必要があります。
法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のある場合は(法人の名称変更や代表者変更など)、変更日から20日以内に届出を行う必要があります。
③書換申請
許可証の記載事項を変更した場合は、許可証の書換えも必要です。
・許可者の氏名または名称の変更
・許可者の住所または居所の変更
・行商する・しないの変更
・法人許可の代表者の交替
・代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
・代表者の住所変更
④期限を過ぎた場合の対応
万が一、届出期限を過ぎてしまった場合は、速やかに所轄の警察署に相談し、指示に従ってください。遅延理由書などを提出することで、罰則を回避できる可能性があります。このケースでは、古物商許可申請にくわしい行政書士への相談がおすすめです。
2)変更届出の提出先
変更届出は、主たる営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。変更届出は、原則として窓口での提出となり、郵送やオンラインでの提出はできません。

3.変更届出を怠った場合のペナルティや罰則
古物商許可を受けた事業者は、許可内容に変更が生じた際、管轄警察署(公安委員会)への変更届出が義務付けられています。この義務を怠ると、古物営業法違反となり、罰金や許可取り消しなどの、ペナルティが科される可能性もありますので注意が必要です。
ここでは、具体的な罰則の内容や、罰則が科される可能性のあるケース、遅延理由書の書き方について解説します。
1)古物営業法違反による罰則
古物営業法では、変更届出を怠った場合の罰則として、以下のようなものがあります。
①10万円以下の罰金(古物営業法第35条)
変更届出を怠った場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
②許可の取り消し(古物営業法第6条)
悪質な場合や繰り返し違反した場合は、許可が取り消される可能性があります。
これらの罰則は、古物市場の健全な運営と犯罪防止を目的としており、違反行為に対しては厳しく対処されます。
2)罰則が科される可能性のあるケース
罰則が科される可能性のあるケースとしては、主に以下の2つが挙げられます。
①悪質なケース
変更届出を意図的に怠った場合や、虚偽の届出を行った場合は、罰則が科される可能性が高くなります。例えば、営業所の移転や名称変更など、事業運営に大きな影響を与える変更を隠蔽した場合などが該当します。
②繰り返し違反した場合
過去に何度も変更届出を怠っている場合や、他の古物営業法違反を犯している場合は、罰則が科される可能性が高くなります。これは、法令遵守の意識が低いと判断されるためです。
これらのケースに該当する場合、罰金だけでなく、許可の取り消しといったより重い処分が下される可能性もあります。
3)遅延理由書の書き方と提出方法
万が一、届出期限を過ぎてしまった場合は、速やかに所轄の警察署に相談し、指示に従って対応しましょう。遅延理由書などを提出することで、罰則を回避できる可能性があります。
①遅延理由書とは?
届出期限に間に合わなかった理由を説明する書類です。遅延理由書は、単なる言い訳ではなく、真摯な反省と今後の対策を示すことが重要です。
②遅延理由書の書き方のポイント
遅延理由、反省の意、今後の対策などを具体的に記載します。遅延理由は、客観的な事実に基づいて具体的に記載し、個人的な事情や言い訳は避けるようにしてください。
反省の意は、今後の法令遵守を徹底する意思を示すことが重要です。今後の対策は、再発防止のための具体的な取り組みを記載してください。
③提出時の注意点
遅延理由書は、所轄の警察署に持参して提出します。提出前に、記載内容に誤りがないか、必要な書類がそろっているかなどを確認してください。また、提出時には、担当者に遅延理由を丁寧に説明し、誠意を示すようにしましょう。
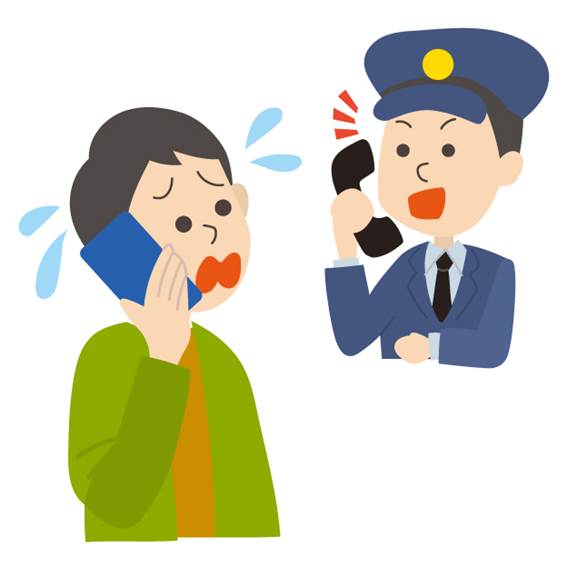
4.変更届出に関するよくある質問
古物商許可の変更届出に関して、多くの事業者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1)変更届出の期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
速やかに所轄の警察署に相談し、指示に従ってください。遅延理由書などを提出することで、罰則を回避できる可能性があります。遅延理由書には、期限内に届出ができなかった理由を具体的に記載し、今後の対策を示すことが重要です。
Q2)変更届出を郵送で行うことは可能ですか?
変更届出は、原則として窓口での提出となり、郵送やオンラインでの提出はできません。これは、本人確認や書類の確認を確実に行うためです。
Q3)変更届出に必要な手数料はいくらですか?
変更届出自体に手数料はかかりませんが、許可証の書換えが必要な場合は、1,500円の手数料がかかります。書換えが必要なケースとしては、許可者の氏名や住所、行商の有無、法人許可の代表者などが変更になった場合が挙げられます。
Q4)変更届出の審査期間はどのくらいですか?
変更届出には、審査はなく、記載内容などに不備がなければ、その場で受理されます。
Q5)変更届出を怠った場合、許可の取り消しは必ず行われますか?
変更届出を怠った場合でも、必ず許可が取り消されるわけではありません。
しかし、悪質な場合や繰り返し違反した場合は、許可が取り消される可能性があります。また、罰金が科されることもあります。変更届出は、古物営業法で定められた義務ですので、期限内に適切に行うようにしてください。

5.古物商許可を維持するために重要なこと
古物商許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。事業者が法令を遵守し、適切な管理体制を維持することが、許可を継続するための重要な条件となります。ここでは、古物商許可を維持するために事業者が留意すべき3つのポイントについて解説します。
1)法令遵守の徹底
古物営業法をはじめとする関係法令を遵守することは、古物商として事業を行う上で最も重要なことです。法令違反は、罰則や許可取り消しにつながるだけでなく、社会的な信用を失うことにもなりかねません。日頃から法令に関する知識をアップデートし、適法な事業運営を心がけましょう。
2)変更事項の適切な管理
古物商許可の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出を行う必要があります。変更届出を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、事業運営に支障をきたす可能性もあります。変更事項が発生した場合は、速やかに所轄の警察署に相談し、適切な手続きを行いましょう。
3)定期的な情報確認
古物営業法や関連法令は、改正されることがあります。また、警察庁や公安委員会から新たな通達が出されることもあります。これらの情報を定期的に確認し、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。情報収集を怠ると、意図せず法令違反をしてしまう可能性もあります。

6.まとめ:変更届出を忘れず、適切な古物商運営を
古物商許可を取得した事業者は、許可内容に変更が生じた場合、公安委員会への変更届出が義務付けられています。この届出を怠ると、罰金や許可取り消しなどのペナルティが科される可能性があり、事業運営に大きな影響をおよぼしかねません。
本記事では、変更届出が必要なケース、届出期限、提出先、ペナルティ、よくある質問などを解説しました。これらの情報を参考に、変更届出を忘れず、適切な古物商運営を心がけてください。
古物商として適法に事業を継続するためには、法令遵守と適切な管理が不可欠です。日頃から法令に関する知識をアップデートし、適法な事業運営を心がけましょう。また、変更事項が発生した場合は、速やかに所轄の警察署や行政書士に相談し、適切な手続きを行いましょう。